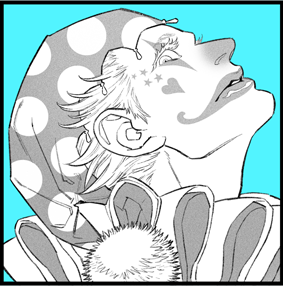真相
捜査は終わった。鬼ヶ島と花木は犯人を指名したところで、階段を降りてくる聴き慣れた足音を聞いた。
シド 「本当にそれでいいのか? まあ、今更変えろというつもりはないけどね」
モノクル眼鏡に癖毛、長身痩躯の男が、気怠そうに歩いてきた。彼こそが、巷を騒がす伝説のサイコメトラー探偵、シド・アップダイクであった。
花木 「先輩、この人はなんでここに来たんですか」
鬼ヶ島 「いいか、覚えておけ。所長はこういう男だ。死ぬほど出たがりなんだよ」
シド 「お前ら、聴こえてるぞ。いいか、直接答え合わせをしてあげようって言ってるんだ。真面目に聞けよ」
ごほん、とシドが咳払いをする。彼は大袈裟に両手を広げるジェスチャーをして、クラブにいた人間の視線を一手に集めた。
シド 「では、一人一人今晩のアリバイを確認していこう……」
シド 「まず、ランディ。アンタは今晩のメインイベントのファイターだったな。どうしても勝ちたかったアンタは、セコンドの男に指示して対戦相手の飲み物に毒を混ぜたな。不調だった対戦相手を打ちのめすのは、いともたやすかっただろうな。それ以外には特に何もしていない。白だ」
シド 「そして、ジョニーだが、そもそもどうやって施設内に入らずに人殺しができる? ジョニーは自分のよく知っている男が死んでいるのを見てその名前を叫んだだけだろ? あと、お前じゃアイアンフィストを倒せないだろ」
ジョニー「うるせえ! お前もそうだろ!」
シド 「続いて、メリー。アンタも補修工事で忙しかった。斜め上を指差したのは、外に備品を買い出しに行った件だ。そして事務所の前に備品を置き、試合中はずっと天井にできた穴の修理を行っていた。そのあとは煙草を吸うか、掃除してたぐらいか? まあ、シロだな」
シド 「さて、残っているのは……クラウン。お前が、このクラブの経営者である初代アイアンフィストを殺したんだ!」
犯人:ザ・レジェンド・オブ・クラウン
シド 「事件の経緯はこうだ……
経営者である初代アイアンフィストは、時間も守らず、人気も低迷してきたことを理由にクラウンを解雇しようと考えていた。その話をするために、クラウンを事務所に呼び出した。
その話を持ち出されたクラウンは逆上し、自身の武器である棍棒で初代アイアンフィストを殴りつけた! ……当然死んだものと思ってクラウンはその場を去ったが、初代アイアンフィストは息を吹き返し、助けを呼ぶためにメイン会場まで這っていったが、結局そこで事切れた。そして死体を皆が発見したというわけさ……」
シド 「何故、誤認が発生したか? 君たちが困惑したアイアンフィストという男だが、その名を持つ人物は実は二人いたんだ。現在経営者をしているのが初代で、覆面のファイターが二代目ということだな。
この事実は、無敗伝説をより長く保つために、ふたりはその秘密を隠していた。しかし、二代目アイアンフィストは今晩のメインイベントでランディに敗けてしまった! 自分が初代に消されるのではという危惧から、彼は急いでこのクラブから逃げ去ったようだ。
さて、次はそこで死んでいる初代アイアンフィストの話に移ろう。
第一発見者のジョニーは、メイン会場に転がっている死体の顔を見て『アイアンフィストだ!』と叫んだ。彼は、同郷の友人が都会で金儲けをしていると聞いて、このKOBUSHIクラブにやってきたわけだからな。そりゃそいつが死んでれば驚くだろうさ。
その言葉を聞いて、身元の確認をしたのがランディだ。だが、ランディたちは覆面ファイターであるアイアンフィストの素顔なんて知らない。重要なのは、腕に彫られた握り拳のタトゥーだ――彼の象徴としてこれ以上なく有名だからな。つまり、彼らにとってもこいつはアイアンフィストなのさ。
そして、クラウンだ。彼は経営者に呼び出されただけだ。俺がさっきから喋っている真相をちゃんと理解しているかは知らないが、クラウン本人としては経営者を殺したという意識しかなかっただろう。だから『アイアンフィストは殺してないよ』と言ったんだ。
以上が事の真相さ……お前たちにはどれくらいわかったかな?」
***
シドが真相を語り終えた。やれやれ、と肩をすくめるような態度を取っているが、彼が毎回こうして事件の関係者全員に注目されるのを楽しみにしているのはあまりに明白だった。
シド 「さて、俺はまたアメリカで仕事があるから、この辺で……」
クラウン「おい」
クラウンがずいっと進み出てきた。無表情でシドを見下している。彼が何らかの凶器を隠し持っていた場合、シドなど一撃で殺されてしまうような間合いだ。場内に緊張が走る。
鬼ヶ島がクラウンに飛び掛かろうとしたところで、クラウンはまた口を開いた。
クラウン「ひとつ訊くぞ、ちゃんと答えろ」
シド 「何だ?」
クラウン「俺が殺したのは経営者じゃなくて、アイアンフィストなのか?」
シド 「だからそう言ったじゃないか」
そうか、そうなのか、と呟きながら、クラウンはシドから距離を取った。自分のしでかしてしまったことの大きさに震えているようだ。
花木「い、一体どうしたんです、こいつ……?」
クラウン「俺がアイアンフィストを殺したんだ!!! ということは、俺が、俺が、俺が、三代目アイアンフィストだあああああああ!!!!」
クラウンが叫んだ。数秒ほど沈黙があったが、すぐに辺りは騒然となった。アイアンフィストの伝説が更新されたのだ――新しい王の誕生を祝い、賭け札や金や酒が怒声とともに飛び交った。
さっきまで神妙なムードだったのが嘘のように、場内にいた客が興奮した。メリーやランディすらも踊り狂っていた。ジョニーは相変わらず仏頂面だったが。
鬼ヶ島「あ、所長……? もう帰ります?」
シド 「……そうだな。付き合いきれないな」
シドはKOBUSHIクラブを後にし、近くのファーストフード店で二人に飯を奢ったあと、空港で別れた。
まあ、今回も一件落着……ということでいいだろう。
***
※これからエンディングの分岐処理を行います。
【エンディングA】
※花木が幽霊の存在を信じ、鬼ヶ島が花木のことを認めた
午後21時30分。南太平洋に浮かぶウンガラバンゴロン島。
ココナッツの生産地として有名なこの島には、もうひとつの顔があった。
コカインの密輸ルートだ。
ラカム 「……絶対許さねえぞ、貴様ら」
長い金髪を後ろにまとめ上げ、不敵に笑う男――ラカム・ジェイコブソンはあらゆる国や地域から目を付けられている大物の密輸業者だ。だが、彼を取り巻く逮捕劇は常に失敗に終わる。証人の不審死、証拠の消滅、裁判の中断……彼の持つ犯罪ネットワークは強大で、誰も彼を追い詰めることはかなわなかった。
だが、それをやり遂げた男たちがいた。
花木 「はいはい、どんな奴も捕まる時は似たようなことをほざくんですね」
鬼ヶ島 「お前にこんな豪勢な別荘はもったいねえ。豚箱でねんねしてな」
簀巻きにしたラカムを地元警察のヘリに乗せた鬼ヶ島は、煙草をくわえた。それにさっと火を点ける花木。
鬼ヶ島 「おう、ありがとうな」
花木 「久々の一服ですね、先輩」
鬼ヶ島 「……まあ、ヤバいヤマだったからな」
一か月以上の大捕り物だった。インターポールだけで何百人関わっていたかもわからない。シド所長も鼻血や血尿が出るくらい能力を使っていた。そんな大事件が、今晩ついに幕を閉じたのだった。
ユラーリィ「大変だったね、ふたりとも」
花木 「ユラーリィは何て?」
鬼ヶ島 「……ねぎらってくれてるよ。こいつだって人一倍頑張ってくれたのにな」
ユラーリィ「なーに、幽霊は疲れたりしないからね、へへん」
花木 「お供えものが要りますか? それか、花でも活けますかね」
鬼ヶ島 「そういうのはウザいらしいぞ」
花木&鬼ヶ島。
このふたりに解けない謎なんて、ひとつもないのだ。
【エンディングB】
※花木が幽霊の存在を信じなかったか、鬼ヶ島が花木のことを認めなかった
事件後、鬼ヶ島満月が訪れたのは、古い仏閣だった。
銀杏並木の参道を歩き、本殿へとたどり着く。着いた先で待っていたのは、一人の僧侶だった。
僧侶 「お主が鬼ヶ島か」
真白い袈裟に身を包み、座禅を組んでいる姿はどう見ても僧侶だ。だが、鬼ヶ島は彼が何者であるかを理解していた。出発前に、シド所長とこんなやりとりをしていたからだ。
シド 「はあ、鬼ちゃんさあ、君が普通の探偵と絡めないのはよくわかったよ。俺の伝手で超ヤバい探偵を紹介してあげるから、そいつと組んでみてくれないか」
つまり、目の前の僧侶は探偵なのだ。僧侶で、探偵。確かにシド所長の言う「超ヤバい」感じはある。
僧侶 「鬼ヶ島よ。貴殿が拙僧とともに巷の事件を解決したいという旨は聞き及んでいる。だが、そのためにはまず貴殿の守護霊を見せてもらおうか」
鬼ヶ島 「……いいだろう」
別に守護霊というわけではないが、ユラーリィのことが伝わってるなら話が早い。俺は雷に打たれたスマホを取り出し、ユラーリィの声を聴かせた。
ユラーリィ「もしもし、デルデルだけど」
僧侶 「ほほう、なかなか可愛らしい霊ではないか……ではこちらも失礼して」
その瞬間、鬼ヶ島の背筋がぞわりと凍り付いた。
僧侶の背後に、幾千という数の妖鬼が現れたからである。
妖鬼たちは揺らめき、踊り、けたたましい笑い声をあげるが、こちらに襲い掛かってくる気配はなかった。むしろ僧侶に従っているような様子だった。
僧侶 「……申し遅れた。拙僧は阿闍梨山有道(あじゃりやまうどう)。八百万の妖鬼たちとともに、未解決事件の捜査を行っているものである!」
鬼ヶ島 「なるほど、これはいい」
俺は直感した。こいつとならやれそうだ。どんな事件にだって取り組める!
俺はスマホをぎゅっと握り締め、志を新たにした。阿闍梨山と握手を交わす。妖鬼たちはいつまでも笑っていた。
***
A この人物を犯人として特定する
B 他の人物の可能性を考えてみる
花木 「犯人は……お前だ!」
花木はコントローラーのボタンを押し、犯人を告発した。犯人は目を回しながらぶっ飛び、つらつらと動機や犯行計画をまくしたて始めた。そのうちに「GAME CLAER」の文字が浮かび、VR機器の電源が落ちた。
花木 「いや~簡単すぎたな」
満足げに鼻息を漏らす花木。その背後にシド・アップダイクがいた。
シド 「じゃあ、今度こそマジの事件行ってみるか?」
花木 「うおおお! な、なんだ所長か、脅かさないでくださいよ」
シド 「VRの捜査訓練ゲームばかりじゃつまらんだろ。これから歌舞伎町で事件だ。ビジョンで視たんだ。早く解決してこい」
花木は思う。その能力があったら、僕たちなんて要らないんじゃないかと……
だが、それを口に出すことはない。本当にお払い箱になったら困るからだ。鬼ヶ島先輩と上手くいかなかった僕は、あれからも結局VR捜査訓練ばかりしており、アップダイク探偵事務所のごく潰し状態であるからだ。
シド 「ああ、そうだ。お前のバディ候補も見つけてきてやったぞ。先に着いているはずだ」
花木 「え、そうなんですか」
シド 「今度は幽霊なんかに頼るやつじゃないからな、安心しろ。普通の男だ」
女性もちょっと苦手なんですよね、と言ったらケツを蹴飛ばされたので、僕は急いで歌舞伎町に出てきた。所長に指定された会員制ラウンジでは、ちょうど常連客の刺殺死体が見つかったところだった。慌てふためく店内で、僕だけが冷静だった。
いや、違う。もう一人冷静な人がいた。
小頭 「どうもどうも! あ、いや、すんません、おれ小頭仁(こがしらじん)って言います。あ! もしかして花木さんですか!? あのKOBUSHIクラブの事件を解決した花木さんですよね? 感激ッス! もうマジでどこにサインしてもらおうかな~?」
小頭は高速でお辞儀をしながら近付いてきた。その間にもこちらを立てるような美辞麗句を百も二百もまくしたてている。ひとつひとつはまるで耳に入ってこないが、聞いてるとだんだん気持ちよくなってくる。
小頭 「いや、すげえッス、ホント、マジで、こんな人と捜査かあ、ワクワクしちゃうなあ、マジで~」
花木は必死に耐えた。ダメだ。探偵たるもの、常にクールでいなければ。調子に乗ってはいけない。
でも、口角が緩むのを抑えられなかった。
花木 「だろぉ~~~? まあまあまあまあ、色々教えてやるからよ! とりあえずこの事件、サクッと解決しちまうか!」
小頭 「うおおおおお頼りになるッス先輩!!!」
先輩。先輩。先輩。
良い響きだ。
花木 「よし、第一発見者は誰だ? 凶器は? 動機は? 僕は、じゃねえや、オレはどんな嘘も見抜けるからよぉ! 大船に乗ったつもりでいろよ!」
所長の人選は素晴らしい。これぞ最高のバディだ。どんな事件だって解決できる気がしてきたぜ……。

—————————–
ゲーム終了――感想戦をお楽しみください!
いかがでしたか? 感想や好きなキャラなど、ハッシュタグ
#コブシクラブ #シド・アップダイク
でつぶやいていただけると、製作者の励みになります!
また、こちらをフォローしていただけると、最新情報をお届け致します。
よろしければシドの直感が冴え渡る他の事件もぜひ体験してみてください。